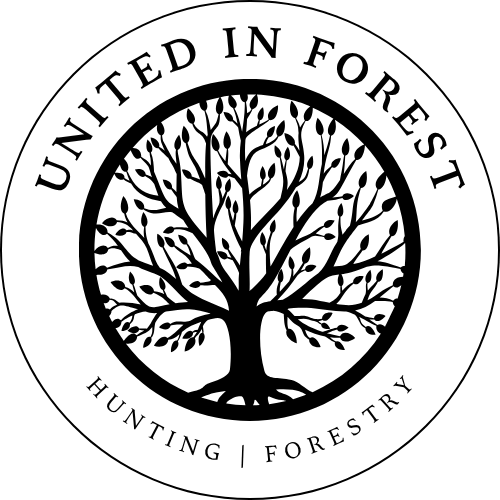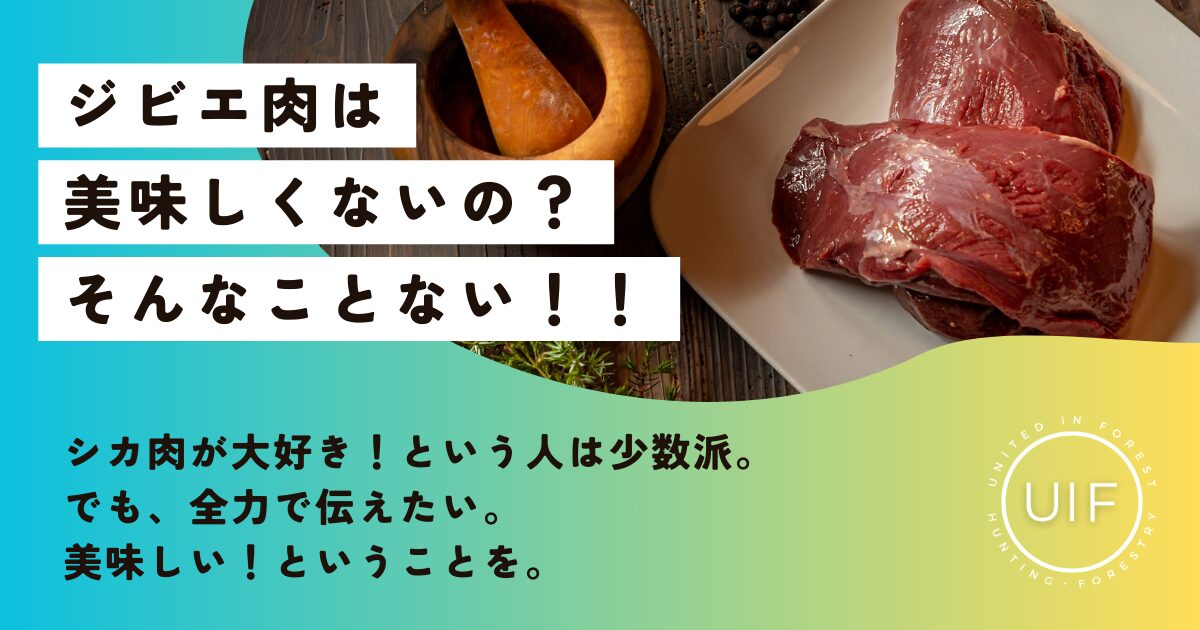皆さんはジビエについて、どんなイメージをお持ちですか。
「クセがある。獣臭い。」
「一部の好事家が食べるもの」
そう思われている方が多いのではないでしょうか。
この記事では、「いまのジビエ肉はとっても美味しい。」ということをお話しています。イノシシ肉には愛好家もいるが、まだまだシカ肉が大好きという人は少数派。でも、美味しいんです。この想いを伝えたい。
その熱量だけで書いています。コーヒー片手にお時間のあるときに、ぜひ読んでいただけたら幸いです。
それではどうぞ。
ジビエ肉=クセがある、獣臭い、不味いは過去の話。
シカ肉は美味しいと、まずは言わせていただきたい。クセがある?獣臭い?それは過去の話です。
シカ肉は美味しい。
大切なことなので繰り返しておきます。
さて、なぜシカ肉(ジビエ肉全般に言えることだと思います。)が美味しくなったのか?
結論から言うと、解体の衛生レベルが格段に向上したから。
一昔前のジビエというと、地元の猟師さんが獲って、我流で解体するのが主流でした。もちろん、統一的な解体マニュアルなどありません。肉の出来栄えは猟師さんのもつ衛生観念と止め刺し、放血の技術次第です。そのため品質が千差万別でした。
そのため、初めて食べたのが「ハズレの肉」(主に止め刺しからの工程が不衛生なために生じる。)だと、「なんか、臭い。不味い。」となってしまいます。
実際、自分の周りでもこうしたネガティブなイメージをジビエ肉に持つ方は多いです。実感としては、年配の方に多くいる気がします。話を聞いてみると、「昔、じいさんが獲っていたので、食べたが美味しくなかった」と言われたりします。ちなみに20~30代は、意外と「シカ肉?食べてみたい!」と好奇心が勝った反応の方が多めです。
まだまだネガティブなイメージが大半を占めるだろう鹿肉もといジビエ肉。その負の印象を払拭するのにも、「ジビエ肉」として広く周知していくことが必要だったのだと思います。
ジビエ肉として一般消費者への認知を広げていったり、HACCPの導入に取り組むなど地道な努力の結果、近年のジビエ肉をつくりあげる解体・加工技術は向上しています。HACCPを小規模なジビエ処理施設でも取り入れるられるようにガイドラインも策定されていて、全国どこでも美味しいジビエ肉は手に入れやすくなっているんです。
Hazard Analysis and Critical Control Point「危害要因分析および重要管理点」の略です。
通称・ハサップと呼ばれています。
原材料の入荷~製造~出荷までの全工程のうち、特に重要な工程を重点的にチェックすることで、全ての最終製品の安全性を確保しよう!という衛生管理手法のことを指します。
危害要因(ハザード)とは、大きく分けると微生物系・硬質異物系・化学物質系の3種類に大別されていて。ざっくり解説すると以下の通り。
・微生物系・・・・・細菌、ウイルス、寄生虫などによる汚染リスク
・硬質異物系・・・・ナイフ類などの欠けた破片や錆びなどが混入するリスク
・化学物質系・・・・ナイフ類を洗う洗剤などが飛散・付着してしまうリスク
これらの危害要因を解体・精肉加工工程で排除または避けるようにすることで、「食品の安全を保つことができる」と考えられます。つまり、この工程の中に3つの危害要因(微生物系、硬質異物系、化学物質系)のどれもが入らないように管理することがHACCPの目的です。
HACCPのおかげで、ほぼ全国のジビエ解体処理施設において衛生的に処理されたジビエ肉がつくられるようになりました。ただし、シカが野生動物ということに変わりはありません。捕獲状況や時期、止め刺しと放血の良し悪しで、品質のバラツキはでてしまいます。それでも、市場にでている製品で、クセや獣臭いなんて感じるジビエ肉は極々稀だと思います。
私も広島・和歌山・奈良などのジビエ解体所を見学させてもらったことがありますが、いずれも肉が汚染(剥皮時の毛や泥や汚れがつくこと。)されないように注意しながら解体・精肉をされていました。
ただし、自分の経験から申し上げると、県内第一号のジビエ解体所などは、まれに危険だったりします。それは旧来のやり方を続けている猟師の方が登録したケースがあるから。
ただし、こうした古参解体所さんでも、ジビエセミナーなどに参加して、やり方をアップデートしていれば問題ありません。
そうしたレアケースもまだあるものの、個人的な経験だけでいえば、ジビエ解体所と呼ばれる場所で適切に処理されたもので、ハズレ肉と呼ばれるようなものに出会ったことはありませんね。
わたしの働くジビエ店でも、解体時また精肉時にも食肉に適さないと判断される肉質のものは弾いています。それは当然ですよね。従来の猟師さんがご近所さんにおすそ分けするのと違い、現在のジビエ解体所ではしっかりと消費者を意識して商品として解体・精肉しているのですから。
どんなお肉ははじくのか、具体的にいうと、解体時に誤って内臓を傷つけてしまった個体や回収に時間を要した個体、捕獲時に既になんらかの病気やケガを負ってしまっている個体などは食用に適さないと判断しています。でもこうして選別した個体もペットフード用に業者に卸すことで無駄にはしていません。
初めて解体・精肉する前に!NG事例を少し。
最後に、解体をこれから狩猟をしていこう!できれば自分で解体もしたい!と考えている方へのアドバイスです。その前にわたしが狩猟免許取りたての頃に参加した講習会の話を少ししていきます。
下の写真は、わたしが猟友会が主催した新規狩猟者向けの講習会に参加したときのものです。この頃のわたしはまだ自分でシカの解体はおろか、捕獲したこともありませんでした。なので、興味津々で写真に収めたりと”非日常”に興奮していた記憶があります。今となっては、こと解体実演に関しては、「ええー!ありえない…!!」と卒倒するような光景です。


というのも、先述べたHACCPやジビエ処理施設で少しでも食肉加工について学んだことのある人にとっては、信じられない環境と手法で解体を実演されていました。
写真の中を例にしてダメな箇所をいくつか挙げるとすれば…
- 露天処理。(自家消費と割り切っていれば、まあOKかも。)
- エプロン不着用。
- 素手で作業している。(手にも雑菌などついているから、手袋は必須!これ絶対!)
- ナイフの柄が木製。(柄は一番雑菌が発生しやすい箇所です。これはHACCPでも、先に説明した危害要因を排除または遠ざける意味でも樹脂製を推奨しています。)
- 写真外ですが、喉と直腸の結紮(けっさつ)がされていない。(胃の内容物が逆流したりするのを防ぎ、肉が汚染されるのを避けるために必要。)
- 剥皮に使用したナイフを、そのまま肉の解体にも使用。(皮に触れている以上、汚染されています。熱湯消毒などして使うのが一般的。)
- ナイフ使用時にアルコール消毒などもしていなかった。(自分たちの例でいえば、肉に触れる恐れのあるものはすべてアルコール消毒しています。止め刺しに使う槍も、もちろん刺す前に消毒!刺した後も血をぬぐって消毒!)
と、挙げたらきりがありませんが、そのくらい今どきのジビエ解体所の解体と加工時には気を使っています。
いろいろと述べましたが、猟友会はあくまで同好の士の集いです。販売用としてジビエ肉を生産している解体処理所と比較するのが、そもそも間違いなのかもしれません。でもこの講習会は、その年に狩猟免許を取得した方が対象です。中には、こうした解体を参考にして、自分で獲った獲物を解体・精肉をして、友人たちにあげてしまうこともありえます!そうしてまた再生産される「ジビエ肉はまずい」という意識。
もちろん、全ての猟友会がそうではないと思いますが、まだまだ食品衛生について気にしない、あるいは重要と思っていない猟師も一定数いるのも事実なんだろうなあと思いました。
猟友会は、あくまで狩猟を愛好する団体であって、肉を加工・流通させる業者ではありません。食品衛生について詳しく学んでいないというのもあると思います。
ですが、自分のご近所さんや友人たちに配るのだとしても、しっかりとした衛生観念をもって解体・精肉することは大切なことだと私は考えています。
自分で獲って、自分で食べる分には、特に気にしないという考え方もそれはそれであると思います。でもでも!できれば、これから狩猟者免許を取得して、捕獲と解体にチャレンジしてみたいと考えている方には、以下に紹介するどちらかのルートで、止め刺しと放血、解体技術について学んでいってもらいたいです。
これから解体を学ぶなら、本で学び講習会を受けよう!
最後に、知識と技術を身につける具体的な方法についてご紹介しておきます。ちゃんとした知識と解体技術があれば、何倍も美味しいお肉になりますよ!
- 『美味しく食べるために狩りをする! ジビエハンターガイドブック』を読む!
- 講習会への参加
一つ目は、本で学ぶこと。
おすすめは『美味しく食べるために狩りをする! ジビエハンターガイドブック』(もちろん、わたしも持っています。)自家消費のためと書かれていますが、衛生的な解体技術について学べる良書です。初めて解体する前と、解体後しばらく時間があいてしまった時など思い出すのに便利です。わたし自身、サラリーマンしながらの狩猟なので運よく週に何度も解体できることがあっても毎週ではありません。少し期間があいてしまった時など復習もかねて読み返すことが多いです。
二つ目は、講習会を受講すること。
ジビエ処理施設が有料で開催している講習会も最近では増えてきています。もし近くにそうした施設があれば、そこで学ぶのが良いと思います。
欲を言えば、本で一連の工程を学んだあとにジビエ処理施設などが主催する講習を受講するのがベストです。あるいは、ジビエ解体施設でアルバイトなどの形で働かせてもらいながら、見てやって学ぶという手もあります。(わたしはこの方法で学んでいます。)
ただし、OJTのように教えてくれる施設なら最高ですが、ジビエ店は小規模な施設が多いため、手取り足取り教えてもらえるというのは、期待してはいけません。
なので、やっぱり本で解体工程の全体像を把握した上で、実際に少しづつ解体処理の補助をしながら技術を習得していくのが王道になります。
ジビエは、止め刺し・放血の技術、解体処理のひと手間、精肉時のひと手間で、ぐん!と素材そのもののクオリティの変わる素晴らしい食材です。
ぜひ、これから狩猟も解体も始めたいという方は、狩猟技術とあわせて解体技術も勉強して、向上させていってもらえたらきっと、楽しいハンティングライフが送れると思いますよ。
また解体・精肉の技術は一朝一夕で習得できるものではありません。でも、繰り返し、繰り返し実践することで必ず上達します。
また、獣害が叫ばれる昨今では、自治体が主催するジビエセミナーなどもあります。私も働いている解体所のスタッフと一緒にジビエセミナーに参加します。もちろん、既に知っている知識もありますが、新たな知見を得られれることもあります。例えばph値での食肉の管理をジビエに活かす話など、数値でお肉の素性を捉えるという視点は気づきでした。
加工技術に関わらず、知識の棚卸と考えて、定期的に学び直すことは大事です。
以下に参考文献やサイトを載せておきますので、ぜひ狩猟と解体を始める前に一読ください。
① 処理活用の技術や事例を学ぶ マニュアル (株式会社一成)
② 『美味しく食べるために狩りをする! ジビエハンターガイドブック』