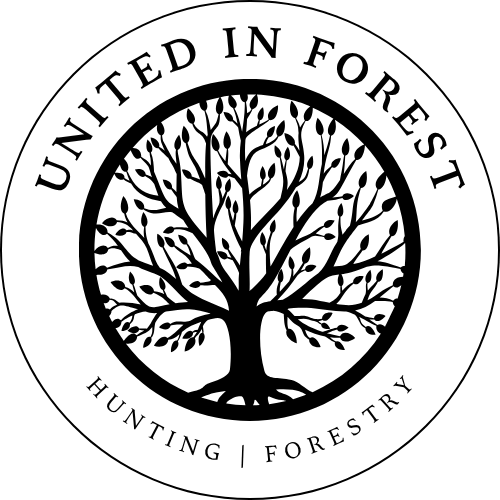先週末ですが、稲刈りと稲架掛けをしました。田んぼはご近所さまのもので、今年は田植えと収穫のお手伝いをさせてもらっています。
来年は、1から自分で田んぼ一枚できたらなあと思っています。でも水の管理とか大変そう。林業も狩猟も田んぼもと、欲張っていますが全部カラダが資本の業なので、より一層体調管理を徹底しなければと思う今日この頃です。
まあ、こんな日の為に、「天穂のサクナヒメ」で米作りの基礎は学んだので、きっと大丈夫でしょう!(ゲームでも良い米作るの大変だったのに、現実だとなおさら難易度高いだろうな…とも思いますが。)
話は稲刈りに戻ります。一昔前までは、稲刈りとなると一家総出、親戚ご近所さんも総動員で一斉に刈り取ったそうですね。この時期だけは「農休み」となって、子どもも手伝っていたそうです。ほんの40
現代は、機械の発達で省人化が進んでいますが、やっぱり数人で一緒に作業するのは楽しいし、気持ちがいいです。(うまく言語化できない。)コストダウンの為には、省人化・無人化が推進される昨今ですが、こうした労働集約型の仕事も残しつつ、良い感じの社会になって欲しいなと、思ったりします。

わたしの住む地域では、足場丸太で架台を作るそうですが、今回は単管パイプで代用。設置も大人二人いればスイスイできます。架台を設置する面だけ、少し手で刈ります。残りはバインダー(刈取機)で収穫するそうです。

3月に引っ越してきてから、半年が経ちました。ひとつひとつ、出来ることが増えていくのは楽しいです。「ネットで調べれば知識は学べても、カラダを使って”実際に”出来るようになるには実践するしかないよな。」と。”知ってたけど、初めてやる”ことが起きる度に思います。
気候変動も、社会の変化もある中で、周囲と助け合えるように、”出来ることを”増やすのは大事ですね。学生時代に働いていたバイト先の店長にも言われました。「チームワークは、そもそも皆が仕事できないと成立しないよ」と。
話が逸れました。完全自給自足を目指すつもりは毛頭ありませんが、ちょっとでも自分で出来ることを増やしていくことって、いつの時代でも大切ですね。
小難しいことはさておき、自分で植えて、収穫したコメを食べるのが楽しみです。